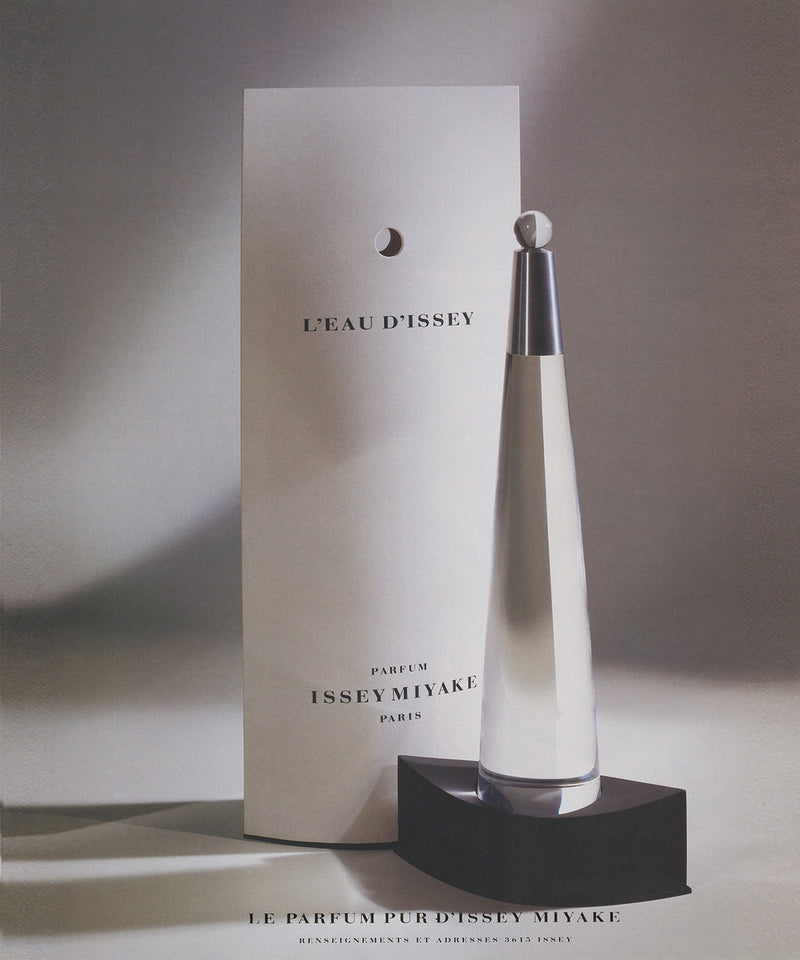Episode 1
“What is Engineering?”
by Manabu Nakatani + Nanae Takahashi
(Design Engineers)
A-POC ABLE ISSEY MIYAKEのものづくりは、エンジニアリングチームが主体となって行ないます。パターンでもテキスタイルでもデザインでもなく“エンジニアリング”。独特の呼び名はもちろん、独特の方法や思考の反映であり、成果はプロダクトやプロジェクトとして表れています。今回はチームの主要メンバーが、その中身について語ります。

“エンジニアリング”とは何か。辞書をひくと大抵はこのようなことが書かれています。「工学。科学的原理を用いて、橋、道路、車両、建物などの機械、構造物、そのほかのものを設計および構築する研究、または仕事」。つまり一般的に衣服をつくり出す仕事とは縁遠い言葉のようにも映ります。
しかし、あるいはだからこそ、A-POC ABLE ISSEY MIYAKE(以下、A-POC ABLE)のものづくりの中心には、エンジニアリングチームが存在する。ものづくりのプロセスごと革新する、というコンセプトを実装するためには、方法や体制もまた既存にはないアイデアが必要であるためで、この背景については、前回のDIALOGUES(Episode 0 “What is A-POC Thinking?”)で語られています。
そこで今回は「エンジニアリングとものづくり」についての具体像により迫っていきます。登場するのはA-POC ABLEのものづくりを牽引する、デザインエンジニアの中谷 学と高橋 奈々恵。どうやらポイントはテキスタイル、パターン、デザインといった領域を自在に横断しながらアイデアを形にすること。そしてその実装のプロセスそのものを設計し構築すること。なるほどどおりで、エンジニアリングと呼ぶわけです。
──今回は「エンジニアリング」がどのように行なわれているかがテーマです。前回のダイアローグでは「なぜ」と問い続けることが、ものづくりのひとつの原動力になるというお話をされていました。まずはこの点についてさらに詳しくお聞きします。
中谷 学(以下、中谷) ものづくりをしていると必ず課題に突き当たります。三宅(一生)がことあるごとに「なぜ」と問い続けてくれたのは、自分だったらどうクリアするかということを主体的に考えさせるためだったんだと、いまでは思います。
私は技術(パターン)としてイッセイ ミヤケに入社しているので、形や線によって解決することは当然模索していましたが、そこにとどまる必要はないんですよね。テキスタイルや加工などからもアプローチは可能だし、いろんなことに興味をもつことができれば、選択肢はどんどん増えていきます。もちろん選択肢が増えていくほどに、パターンとの向き合い方もよりフレキシブルになっていきました。
──もともとは「なぜ」を考えるようなタイプではなかったのですか?
中谷 そうかもしれません。とにかく服をつくりたいという衝動に身を委ねるようなところがあったというか。それを見抜かれていたんでしょうね。三宅だけでなく先輩たちからも、耳が痛くなるほど「なぜ」と問われていたのは。それにしっかり答えるには、選択肢だけでなく、その服をつくる目的や方法が自分の中にしっかり備わってないといけない。
「これをやってきて」と言われたときには、「なぜこれをやるのか」という思考が不可欠なんです。言われた通りにただやるだけでは、視野も拡がらないし選択肢も増えていかないですから。だからやっぱり「なぜ」はものづくりの原動力になります。

(A-POC ABLE ISSEY MIYAKEのデザインエンジニア、中谷 学)
──高橋さんは「なぜ」という問いかけと、どう向き合っていましたか?
高橋 奈々恵(以下、高橋) そういう点では、私は中谷とは逆ですね。最初はPLEATS PLEASE ISSEY MIYAKEに配属されたのですが、「なぜ」と思うことはすでにたくさんありました。「プリーツ加工前の服にしつけ(※)をしてるのはなぜだろう?」とか「プリーツ加工を施す際に紙をはさまなくてはいけないのはなぜだろう?」とか。目の前にあるものづくりのプロセスに対して、いろいろな疑問をもっていました。
だから私が技術として最初から最後まで課題として考えていたのは、製造工程からしつけをなくすことでしたね。2年半で配属先が変わったこともあって、結局は解決することができませんでした。
──キャラクターの異なるふたりがエンジニアリングデザイナーとしてA-POC ABLEのものづくりを支えているのも、ユニークな点のひとつなのかもしれません。テキスタイル、デザイン、パターンと分業するのではなく、領域を横断したものづくりの魅力を教えてください。
高橋 ブランドに求められていることや世界観によっては、これまでの分業したスタイルのほうが適していることもあると思います。けれどA-POC ABLEにおいては、一枚の布から、または必要であれば一本の糸からストーリーをすべてつくることができるんですね。
パターンだけしかできないと、ときどき「どうしてこの生地でこのデザインなんだろう」という葛藤が生まれてしまうことがあります。食材とレシピの組み合わせが最適ではないように感じるというか。パターンだけではどうしても課題を解決しきれないもどかしさが残されてしまうというか。
中谷 イッセイ ミヤケに入ったばかりの頃は、「この布でこの形を作ることは難しい」とか、高橋のように違和感を抱くことは難しいのかもしれません。けれど先程お話しした「なぜ」を考え続けながら経験を積んでいくと、そういうことに気づけるようになります。そして違和感を抱くだけではなく、求められた形にするための方法や、もっとこういう形のほうがいいのではないか、あるいはこういう素材にしたらどうか、という提案も考えられるようになっていく。
もちろん素材のことを口に出すには、かなり学ぶ必要があります。同じ糸を用いても織り方や打ち込みでまったく違う生地になっていくので、経験を積んでいないとテキスタイルの人たちと具体的なコミュニケーションをするのも難しいですから。けれどテキスタイルという選択肢も自分の視野に入ってくると、さらに可能性が拡がっていきます。
さまざまな領域で学んだ経験と情報を理解して、自律的に考えていくことができれば、服づくりはどんどん自由に楽しくなっていきます。さらにお店のことやビジネスのことも考えることもできていきます。

(A-POC ABLE ISSEY MIYAKEのデザインエンジニア、高橋 奈々恵)
──つまりものづくりを俯瞰して行なうことができる。それがA-POC ABLEのエンジニアリングの魅力のひとつですね。
高橋 そうですね。技術の仕事で培ってきたことを技術だけで終わらないで、しっかりとデザインやテキスタイルにもつなげていく。そこを横断していけるから面白いことができるような気がします。「エンジニアリング」というと工学的なもののようで、服をつくることとは少し違うニュアンスかもしれないけれど。
中谷 確かに。けれど工学や構造設計という点でも、それに似たようなことを私たちは行なうこともあります。先程、高橋が「しつけをなくしたい」という話をしていましたが、品質を落とさずに製造のプロセスをいかに更新するか、というのも大切にしていて。例えば縫製がもっと簡単になるにはどうしたらいいかとか、縫い代の情報を布に織り込んでおけば、もっと効率よくなるかなとか。そういうことを考えたり実装していくのも、すごく楽しいですね。
──衣服に表れないような、その背後にある製造の工程にまで視野を拡げていく。
中谷 そうですね。すでにレールが敷かれていれば、それを続けていくことができますが、私たちのものづくりはレールがないところに新しく敷いていくような仕事でもあるので。言葉にするのは簡単ですが、当然簡単な仕事ではないし、そのぶんやりがいがあるし、それが実際に形になったときの喜びも大きいですね。
自分のものづくりというよりも、“ものづくりの環境そのもの”や“新しい可能性”そのものをつくることになるから。A-POC ABLEにおいてはその価値を大切にしています。そうでなければ、私たちの服をつくり続けることはできないと思うんです。

──ブランドのコンセプトにある「服づくりのプロセスの変革」というものが何を表しているかがわかってきました。
中谷 工場や職人さんも私たちのものづくりのチームですから。既存にはない方法を模索したり探求したりしていくので、最初からスムーズにはいきません。それでも本気で向き合い、時にはぶつかり合ったりしていくことで、お互いに理解を深めていくことができるんだと思います。いまでは縫製とか加工とか、さまざまな工程で、日本中にスペシャリストたちがいます。
──そういう環境をつくっていく際に、大切にしているのはどのようなことですか?
中谷 厳密すぎるルールをつくらないことでしょうか。「こういうものがつくりたい」というゴールを明確にして、そのためのプロセスやレシピもある程度は提示します。けれどその先は工場の人たちにある程度お任せする。もちろんうまくいかない時は、こちらでも再検討して提案したりもしますが、より効率がよくやりやすい方法があれば、そのようにどんどん変えてもらいます。従来の方法であれば指示書をもとに「こうしてください」というだけですけれど、それに囚われてしまうと、思考も停止してしまうし、新しい可能性に蓋をしてしまうので。
──放任ではなく自律的な関係性と言うこともできそうです。ものづくりの可能性を拡げていくにはとても有効な方法だと思いますが、構築は決して楽ではないですね。
中谷 回答になっているかわかりませんが、自分が何かものをつくり出そうとする時には、その生産を担ってくれる工場の人たちの顔が浮かびます。ですから「どうやったらもっと縫いやすくなるか」とか、「こうしたほうがスチームを当てやすいか」とか、工場のやりやすい方法を考えたいし、それをプログラムとして布に織り込んで形にしていくことを、いつも考えているように思います。
パターンだけではなく、どういうプロセスで生地になり、縫製され、加工されていくかというところまで視野が拡がっているからこそ、それができる。単純にものをつくるだけなら、縫いにくいとか、量産が難しいとか、そういうことを気にしなくてもいいかもしれません。けれど私たちは、「あとは誰かがどうにかしてくれる」を良しとはしません。ものづくりのプロセスそのものをできるだけ「一枚の布」に埋め込んでいくからです。それによって例えば縫いやすくなり、それでも着心地も価値も変わらないようなことが起きると、すごく楽しいと感じるんです。
高橋 そうですね。私がかつてしつけをなくしたいと思ったのも、そういうことだったと思う。ほかにも例えば工場ではなく伝統的な染色の職人さんとものづくりをするときも、最初から私たちが目指しているような関係性を築くことはできません。
受け継いできた歴史が長かったり、熟練の方であればあるほど、それまでやってきたことから外れることを依頼するのは難しい。けれど私たちは新しい可能性を模索したい。少しずつ工房に通いながら、お互いを理解し合えるようになるまでに、数年、時には6〜7年を要することもある。そうやって関係を深めていくなかで、一緒になって何でもチャレンジしてもらえるようなチームになっていきます。

中谷 そうやってできることを増やしていく。私たちはその先にある未来を見たいと思っているんです。そのためには、いまつくりたいもののことだけでなく、それをどうやって誰とつくるのか、それによってどのような新しい可能性が生まれるかを考える。同じ機械で同じようなことをしていても、同じようなものしかできません。けれど少しずつでも新しいことを工場や職人さんと探求していく。そのために最適な環境や関係性をつくっていくのも、私たちの仕事です。
──新しいプロダクトをつくるだけではなく、それによってできることを増やしていくこと。A-POC ABLEのエンジニアリングという具体像が見えてきたようです。そのために視野を拡げ、選択肢を増やすことが必要なんですね。
中谷 逆説的に聞こえるかもしれませんが、選択肢が増えるほどに引き算がうまくできるようになっていきます。足し算をして高付加価値のものを生み出すのも素晴らしいと思いますが、シンプルに研ぎ澄まされた高品質なものにも魅力がある。どういったお客さまがどういうところで着たいと思えるか、その目的のために純度の高いプログラムを考えることができますから。
そんなふうに考えられるようなると、ものづくりのためのものづくりに陥らないですみます。「お客さまの喜ぶ表情までをデザインできるように」。最近、三宅が言っていたこの言葉をよく思い出すんです。着る人の表情を想像したり感情を理解したりして服をつくることができれば、よりピンポイントに引き算をしたものづくりができていくように感じる。それがとても面白い。
高橋 わかります。引き算の面白さ。新しく興味をもって着ていただくためにもシンプルさは大切だと思います。それに不思議なことに、A-POC ABLEの服はシンプルにすればするほど、実際にはそのものづくりのプロセスや三宅の考え方のようなものが浮かび上がっているようにも感じます。服は誰かの何かのきっかけになるものだと思います。エンジニアリングを通じて、着てくれる人も、つくる人にも何かきっかけをもたらしていきたいですね。

※「しつけ」という言葉は日本独自のもので、着物を仕立てる際に折りが崩れないようにするため、袖などに縫い施す作業のこと。PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKEにおいては、プリーツマシンでプリーツをかける際に縫製済みの前身頃と後身頃の生地がずれないように糸を縫いつけることを指します。
次回のEpisode 2では“Freeform Design”についてお届けします