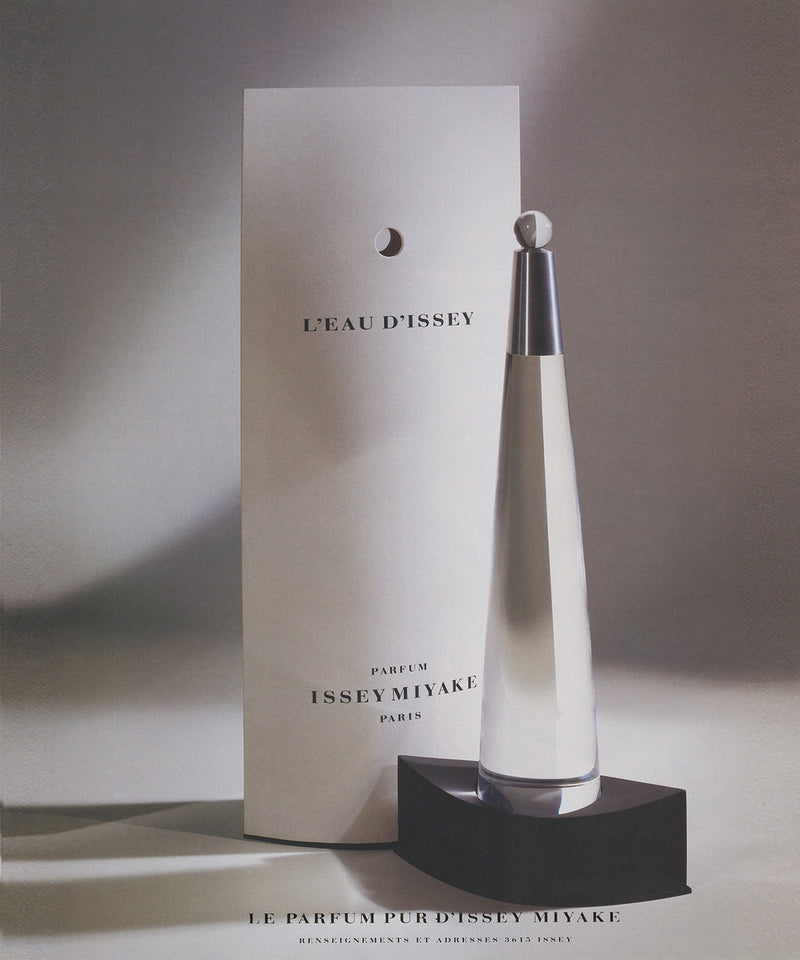Episode 7
“Taking Detours with AI”
by Kazuya Kawasaki+Kotaro Sano (Synflux)
人工知能は社会のさまざまな領域に実装されつつあり、ものづくりの現場においても無縁ではありません。SynfluxはAIや3Dモデリングといった先進のテクノロジーを活用し、持続可能でより創造性に富んだデザインシステムを開発するラボラトリー。A-POC ABLE ISSEY MIYAKEとの協業で「TYPE-IX Synflux project」を手がけています。このプロジェクトの背景にはどのような技術や思考、そして未来へのプロセスが宿されているのでしょうか。CEOの川崎和也、COOの佐野虎太郎とともに対話を深めていきます。

常識を打ち破るかのような、大胆な切り替えが衣服の縦横にめぐっている。「TYPE-IX Synflux project」によって生み出された2型のジャケットには、どうやらこれまでになく多元的な“情報”が埋め込まれているようです。テキスタイルのロスを低減させる合理性、衣服としての機能や意匠、そして来たるべきAIの時代における創造のあり方。
A-POC ABLEの独自の形状記憶素材「TYPE-U」のジャケットを原型にしたこのプロジェクトは、Synfluxが開発したデザインシステム「Algorithmic Couture」によって膨大なパターンのシュミレーションを生成し、エンジニアリングチームや開発者が評価/解釈する。その試行錯誤を繰り返しながら進んでいきました。つまりこの複雑で合理的でもあるパターンは、アルゴリズムと人との対話の成果です。
もちろんひとつの理想とするパターンは、既にデザインエンジニアの手によって引かれている。それでもなお、より美しく無駄のない線を引くことはできるのか。Synfluxが開発したアルゴリズムというテクノロジーとの出会いによって、A-POC ABLEのものづくりのプロセスは、新しい問いと向き合うことになりました。今回の対話はそのきっかけとなった出来事から始まります。
──川崎さんと宮前さんの出会いのきっかけになったのは、2020年に開催された「TADANORI YOKOO ISSEY MIYAKE 0」の展示だったそうですね。
川崎和也(以下、川崎) そうです。あの「A-POC」を宮前さんが復活させるということが、私たちにとってはビッグニュースでしたから。横尾忠則さんとの協業を展示されると知って、代官山T-SITEのギャラリーに行きました。圧巻でしたね。ブルゾンを着ているのは3Dプリンターでつくったマネキンで、横幅1800mmのテキスタイルがダイナミックに展開されていて。色使いもパターンも想像を超えるものでした。とにかくずっと「すごい!」「なんでこんなことができるんだろう」と口をついて出ていました。それで共通の知人を介して、宮前さんとお話しする機会を得たんです。
──その頃にはもう「Algorithmic Couture」は開発されていたのですか?
川崎 システムの開発は始まっていましたが、まだ卵というか、その手前の胚のような状態でした。それでもどうしても宮前さんとはお話したかった。そもそも私は学生の頃から、三宅一生さんの言葉にとても影響を受けていたので。例えば、1960年の世界デザイン会議が開催される際に、当時学生だった三宅さんが「なぜ議題に衣服の分野が含まれないのか」と質問状を事務局へ送付したという有名なエピソードがありますが、あれはきっと、生活や社会をかたちづくるものとしての衣服、そのためのデザインという考え方があったからですよね。
私もファッションの表象的な部分よりも、ものづくりやそれを支えるものとしてのデザインに、ずっと関心をもってきたので、三宅さんのそういった行動や言葉にはとても影響を受けています。クリエーションという便利というか謎に満ちた言葉があって、ときにファッションはそれによって魔法のように衣服を生み出すかのように語られたりもしますが、私たちの生活のなかの衣服はきっと、そういうものだけではないはずですから。
それに「一枚の布」という三宅さんの言葉への共鳴もあります。この言葉はつくり方だけでなく思想でもあると思いますが、私たちのアルゴリズムを応用したデザインシステムも、いかに布を大切に使うかとか、幾何学やコンピュテーショナルな方法論をどうやって布や衣服の設計に反映していくというミッションがもとにあるので、重なる部分が大いにあると考えていました。なので、宮前さんがA-POCを復活させたと聞いて、いてもたってもいられず、提案させていただく機会を得たんです。

宮前 義之(以下、宮前) いまお話しいただいたみたいに、とにかくたくさんイッセイ ミヤケのことをリサーチされていて。提案していただいた内容もとても素晴らしかったし、新しい視点を得られると感じました。私たちがA-POC ABLEでやろうとしていた「ものづくりのプロセスから革新していく」という目的のためには、ものづくりの川上から川下までを俯瞰して横断して考えていく必要があるので。
例えばサステナビリティといった業界全体で取り組む必要がある問題であっても、既存の構造の中だけで解決していくのは難しくなってしまっています。非常に専門性が高い領域が相互に影響し合っていて、その一部を解決する方法があったとしても、実行するには全体を最適化していかなければならない。だから川崎さんのようなこれまでになかった異分野の知見や技術によって、これまでにない新しい視点でものづくりを俯瞰していくことに、とても可能性を感じたんです。
なにしろAIやアルゴリズムといった、これまでの人間とは異なる知能をもとにしたテクノロジーですから。僕たちが想像し得なかったような手段や方法が生み出されていくこともあるだろうし、その一方で、実際にものづくりのどういった部分を担っていくことができるのか、わからないところも大きい。だからまずは川崎さんたちと会話をしながら、当初はゴールも設定せず、ゆっくりとプロジェクトをスタートしていくことになりました。
──これまでのさまざまな協業のプロジェクトと同様に、まずは会話をされていったんですね。
宮前 そのつもりだったのですが、川崎さんのプレゼン力がすごくて(笑)。どんどん新しい提案が出てきました。そこには当然、私たちと合うものと、ちょっと合わないものもありましたが、とにかくたくさんアイデアが出てくるのが新鮮でした。
形や色のユニークさを追求するようなプランもあったし、それについてはアルゴリズムという身体をもたない技術ならではの可能性も感じました。けれどSynfluxにはものづくりのプロセスのなかで、テキスタイルの廃棄やロスを減らしていく、という明確なミッションがあったので、まずはその目的を私たちの技術と掛け合わせながら解いていくための例題を設定することにしたんです。それがA-POC ABLEの最もベーシックなジャケットのひとつである「TYPE-U」でした。
川崎 今回のプロジェクトがドライブしたなと感じた場面がいくつかあるのですが、そのひとつがいまの宮前さんの言葉でした。「TYPE-U」のジャケットという、生活のなかでしっかりと根付いているような、普遍性のあるプロダクトをターゲットにしようと。これを起点にすることで私たちはアルゴリズムをより自由に活用できるようになったと思います。
ふたつ目は、ISSEY MIYAKEの初期のコレクションに「包丁カット」(三宅一生が料亭の板前の包丁さばきからインスピレーションを得たカッティング)というものがあるのですが、それを関連づけてプロトタイプをつくっていこう、と話していただいたことですね。今回のプロジェクトでAlgorithmic Coutureが生成するパターン線の意味が、そこではっきりとしていったというか。
──あらゆるパターンを生成することが可能だからこそ、意味が必要だったんですね。
川崎 AIは統計と推論は得意ですが、身体をもたず意味を理解しない技術です。一方でファッションや衣服はそのどちらもが絶対的に必要。だからこそファッションとAIは掛け合わせるのが難しいとされている理由でもあります。一方で、意味や文脈が我々のなかに生まれてくると、アルゴリズムで生成させるためのパラメーターを方向づけたり、生成されたパターンを評価したりすることが可能になるんですよね。
さらにもうひとつ、印象的な場面があって、それは中谷さんが「もうここからはパターンで会話しましょうか」とさらっと言ってくださったことです。そうして実際に私たちがパターンを生成して、みなさんからフィードバックをいただくという試行錯誤が始まったわけですが、そのやりとりのなかで、A-POC ABLEが大切にしてきた細かなディテールやルール、私たちが学習できていない服づくりの生産現場で行われていることなどが、どんどん顕在化していきました。ようするに「ものづくりによってはじめて、データに身体性が通うということ。ものすごい情報量が詰まった服と向き合わないといけない」ということです。
──なるほど。中谷さんはなぜ「パターンで会話しよう」と話したんですか?
中谷 学(以下、中谷) 私たちにとっても、アルゴリズムや人工知能のような技術と協業するのは初めての経験で。いままで守ってきたものを否定するわけではないですが、3Dモデリングなども含めて人の手から離れるような技術は、どこか避けてきたようなところもあったし、飛び込む勇気を必要としていた領域だったのかもしれません。その点でいうと、川崎さんからはすごく熱意を感じましたし、私たちもその熱意に対して熱意で飛び込んでみようって思うことができたというか。自分に言い聞かせるような意味もあったのかもしれません。
良くも悪くも服づくりはある程度、流れが決まっています。布をつくり、パターンを引いて、裁断して、縫って、加工をする。そのなかの途中の段階に、まったく新しい技術が入ってくるということだから、それはきっとどこかの過程で問題を生じさせてしまうかもしれない。そのどこかというのが、私たちの領域ではなく、その前後のどこか。そういった人たちにネガティブなことが起きる可能性も考えてしまうんですね。
その一方で、先ほど川崎さんは「胚のような状態」と言っていましたけど、そのような状態からようやく形が見えてくるようになっていった。そういう過渡期のような技術は、自分たちだけで前進させていくのは難しいと思うんです。まったく新しいテクノロジーだから、既存の方法論やお手本もないわけで。どこに進んでいいかも見えてこないことだってある。そういう時、私たちのような異なる視点をもつ人間とコミュニケーションをとっていくと、お互いに刺激となって、新しい方向性やアイデアが生まれてきたりしますよね。なんというか私もそういった瞬間が見たくて、一緒にやっていきたいと思ったんです。
──AIやアルゴリズムのような先進的なテクノロジーを、ファッションやものづくりを掛け合わせていくとき、川崎さんが目指していく方向性はどのようなものでしょう?
川崎 服づくりという側面でいえば、例えば「デジタル技術がすべての作業を自動化します」とか、「AIがデザイナーに取って代わる」といったヴィジョンを掲げるのは無謀だと思っています。
むしろ私たちが重要だと思っているのは、ファッション産業で働く人たちと、衣服と技術の関係性を再構築するっていうことなんです。数百年間にわたって連綿と積み上げられてきた服づくりの技術があって、私たちはその恩恵を得ているわけですが、全体を見渡すとある意味でガタがきているようにも見えます。サステナビリティもその顕著な例ですが、先ほど宮前さんが言っていたように、どこから変えていったらいいのかわからないほど、とても複雑な問題になっています。
つまり部分ではなくて、全体の関係性を見直していく方がいい。そこにSynfluxやAlgorithmic Coutureが介入していくと、いろいろと考え直す必要が出てきます。我々やテクノロジーが媒介となって、そういった関係性の見直しのきっかけをつくっていく。それだけじゃなくて「とりあえずやっていきましょう」という行動にまで繋げていく。それがやりたいことのひとつです。もちろんその成果として、最適化や自動化や持続可能性の向上ということも促されていくと思うのですが、まずはひとつの変化を生み出すきっかけとしてAIやアルゴリズムを使っていきたいんです。
──これによってこういう成果が生まれる、ということよりも、これまでになかった変化を生み出し、その可能性に気づいてもらうために先進的なテクノロジーを使うということ。
佐野 虎太郎(以下、佐野) そうですね。何かを解決する手段であることももちろんですが、新しいコミュニケーションのためのアクターがひとつ増えるみたいな感覚に近いのかもしれません。
川崎 いまでこそAIやアルゴリズムは新しいハイテクノロジーですが、やがてはハサミやミシンのようなものになっていくと思うんです。それらも生まれたばかりの頃は、かなりハイテクノロジーだと捉えられていたはずですから。つまりAIも道具になっていく。だから結局は、その道具をどうやって面白く使うかという人間の話になっていくんです。
現状、あらゆる産業においてAIに期待されていることといえば、合理化、自動化、軽量化、省力化といった定量的な問題の解決がほとんどだと思います。けれどファッションや衣服が面白いのは、「計算不可能性」が大切にされているということです。減らせました、軽くなりました、コスト抑えました。それはいいことかもしれないけれど面白いことではない。私たちが知りたいのは、いい衣服とは何かということだし、それに出会えたと思えたとき、すごく感動します。今回のプロジェクトでは、A-POC ABLEのみなさんとのやりとりを通じて、それをいつも教えてもらったんです。
──アルゴリズムが生成したパターンと向き合う経験は、初めてだったと思いますが、いかがでしたか?
宮前 私たちが求めていたのは合理的に最適化されたパターンではありません。自分たちが想像し得ないようなパターンです。そこへどうやってアルゴリズムを導いていくか、という期待がありました。そういうプロセスは当然初めてだったので、とても新鮮でしたし面白かった。なんだかチームにまったく異なる能力を持った人が入ってきたような。
高橋 奈々恵(以下、高橋) 初めに通常のパターンから3Dのモデリングデータをつくってお渡しして、それをもとにアルゴリズムが新しいパターンを引いていくという作業でした。最初に出されたものを見たときは、「これは大変だ」と思いましたね(笑)。曲線という概念がなくすべて直線だったし、よく言えば自分が試されるほど斬新。あるいは、服飾学校の1年生。
佐野 そうでしたね(笑)。まず最初に切り替えの入り方が異なるパターンを何百、何千と生成して、その中から我々のほうで取捨選択して、淘汰して数を絞り、絞った中からまた拡げて、それを取捨して狭めて、というようなプロセスを繰り返して出てきたパターンを見ていただきました。ですが、そもそもアルゴリズムはアームホールの意味、つまり「このトポロジーは肩が入って大きく動く場所である」ということを理解するのが難しいので、なかには既存の衣服の作り方のルールである「構造線」が大きく変えられているようなパターンもありました。
宮前 けれどそのような状況が私たちからしたら面白かったのも事実です。固定概念を外させてくれるので。そもそもこのプロジェクトは視点を変えるという目的もあるわけですから。もちろん、評価したり選択していくのは僕たちなので、すべてを委ねることはありませんが、服として求めていることはしっかりあり続けながらも、いつもと違った感覚で向き合っていくようでした。
──そのようなフィードバックをもらったあとは、どのうようにアルゴリズムに反映させるのですか?
川崎 技術を制御するべきポイントが明らかになってくるので、それが生成されないようにパラメーターを変化させていきます。しかしそうすると、また新しいミスというか予想外の切り替えが生まれたりするんですよね。今回のプロジェクトが面白かったのは、そのような想像もできないような線と、A-POC ABLEのみなさんが正面から向き合って評価してくれたところです。
通常は目的が決まっていて、こういう意匠や切り替えがほしいから、そのためのパターンを出してくださいという流れになる。けれど今回は、アルゴリズムが生成したものに対して、衣服のスペシャリストたちが「こういう解釈もあり得るかもね」という受け入れ方をしていってくれました。その差はとても大きいし、すごく新しい試みだったと思います。
──まるでアルゴリズムと一緒に、あえてまわり道をするようなプロセスですね。
川崎 たしかに。正確で無駄のないジャケットをつくるということではなく、どのようなパターンの可能性があるかを探求するようなプロジェクトでしたから。まずはたくさん生成して、みんなでうーんと考えて、会話をしてフィードバックしていくというプロセスだったので。
宮前 先日、お会いしたときに、川崎さんと山登りの話をした気がするんですけど、山登りと一緒のような気がします。同じ山登りにしてもいろんな道がある。例えば中谷や高橋には「こっちから行ったほうが早いでしょう」という知識や経験や感覚によって培われた方法論をもっています。それでも時には、あえて別の道を模索してもいいんだと思います。その中でこそ新しい視点や可能性が生まれるので。
高橋 わたしはとても面白かったですよ。例えば肩の継ぎ方とか、襟のはぎとか。普通のパタンナーなら絶対考えないような線を出してくるので。わたしたちからしたら「これどうやって縫うの?」っていうのもたくさんあったけど、出してもらうことが重要だったと思う。それに何万通りもシュミレーションできるというのは、わたしたちにはない強さだとも感じます。
──これまでになかった方法でアルゴリズムとものづくりの関係性を徹底して模索したプロジェクトだともいえそうです。
中谷 そうかもしれません。私たちはA-POC ABLEのものづくりを通じて、身体と衣服の関係性や、構築的なフォルムの造形には向き合うのですが、今回の生成されたパターンのように、その成果物とチームで向き合うような時間はあまりなかったんだなと、気づくことができました。
衣服を視覚的要素で分解していくと、線一つ切り替えるだけで見え方もまったく変わってくるし、そうやって新しい線の価値みたいなものが生まれてくると思うのですが、それを今回のプロジェクトのように見つけていく作業というのは、あまり僕たちがやってこなかったことでした。
さらに飛躍して考えていくと、例えばいま存在しているパターンというのは、ある程度、天然繊維の生地に対する縫製基準にのっとったかたちになっている。けれど素材もかなり進化してきたし、ストレッチやニットや合成繊維のテキスタイルがあるなかで、縫製すべき場所や線というのも変化していいのではないか、という動きもあったりします。それはつまり、どこでどういうふうにカットして、切り替えていくのかを考えていくことは、これまで以上に重要になってくるということです。そのためにも今回のように、とにかくたくさんのバリエーションを出していくのは、とても可能性があることだと思います。
川崎 アルゴリズムは量とバリエーションは得意ですからね。恥ずかしがらずに、どんどん出してくれます。
宮前 恥ずかしがらないっていいですね(笑)
高橋 本当に。それはものづくりでとても重要なこと。
川崎 アルゴリズムはピュアなので(笑)。ひたすらつくりたいんです。
佐野
AIやアルゴリズムと、衣服やファッションについて考えたときに重要だなと思ったことが、2点あります。ひとつがいま話されてるような、フラットに無機質に出してくるという特性を、どうやって人が解釈で面白くするかということ。今回のプロジェクトで我々人間からのフィードバックは、まさにその作業だったと思います。
もうひとつは、「AIやアルゴリズムには身体がない」ということです。その身体がないAIとどのように衣服をつくるのか。とても難しい問いだからこそ面白いですよね。身体がないテクノロジーにとっては、究極的には着心地がいいということを理解するのは難しい。だから実現できないと思考を止めるのではなくて、その技術を使う我々がどんどんアイデアを出していく。入力する数値を面白くしたり、お題そのものの発想を豊かにしたり、少しガイドをしたり、ずらしたり、再解釈していく。つまりAIをユニークに使う方法を考えざるをえないということです。今回のプロジェクトはそれに改めて気付かされました。
──さまざまな気づきや視点が生まれたようです。今後はどのように展望していますか?
宮前 川崎さんや佐野さんが言うようにまったく新しい道具ですから、これからもどんどん新しい使い方が出てくるだろうし、どのような表現が出てくるのか、とても好奇心が湧いてきます。新しいテクノロジーを使ったときに、私たちしかできない表現は何だろうかと。そういうことを考える起点になると思うんですよ。
もちろん使い方によっては状況がより悪くなったり、自分の仕事がなくなってしまうというようなネガティブな想像もできてしまうけど、私たちものづくりに携わる人間は、どのように可能性を拡げて、ポジティブなことができるかを考えるべきだと思うんです。もちろん今回のプロジェクトではそのようなところまで行けたわけではないですが、まずはこの新しいテクノロジーを道具として私たちが何ができるのかを考えていくいい機会になったと思います。
川崎 私たちの目的は、21世紀の服づくりを実装していくための、プロセスや技術でありたいと思ってるんですね。なのでもちろんできるだけ合理的で、廃棄やロスの出ないつくり方というものを、Algorithmic Coutureで実現していくために開発を継続してます。一方でこれまでお話ししたように、服にはさまざまな要素があるし、今回、A-POC ABLEのみなさんとのプロジェクトでは、一枚の布のなかに、とてもたくさんの情報や価値が落とし込まれていることを知ることができました。そういったことも大切にしながら活動していきたいですね。
──身体をもち得ないAIは、ファッションやアートピースなど斬新な形を生成するほうが、生活のなかの衣服をつくることよりも、あるいは得意なのかもしれません。それでもなおSynfluxがものづくりの現場やデザインに接続していこうとするのはなぜですか?
川崎 それは私たちの目的のためですね。やはり私が見たい未来というのは、システムやインフラが変わることで、面白い表現やプロダクトが生み出されていくことなんです。個人のデザイナーの素晴らしい創造性やアイデアによって、美しい服が生み出されていくという方法は、既に完成されているように感じていて。
けれどそういった方法だけではシステムやインフラの部分にある問題、つまりプロセス自体を見直したり新しくしていくのはどうやら難しい。なので私たちが新しいテクノロジーを活用しながら改善していく。そうなったときに、どんな衣服が生まれるのかが見たいからこそ、それを実現していきたいんです。
宮前 システムやインフラの革新こそ、美意識をもった人がやるべきだと思うんです。川崎さんや佐野さんに期待しているのは、その点です。これまではシステムやインフラ、ビジネスやプラットフォームをつくる人と、美意識を発揮する人が分かれていたように感じます。それによって大量生産と大量消費が加速した面もあったかもしれません。
けれどこれからは、しっかりと美しいものをつくるために、新しい仕組みを考えて構築できる人が必要になってくると思います。ものづくりの全体を俯瞰して、横断していくためには、そのようなハイブリッドな感覚が大切になってくるはずですから。それを一緒にやっていきたいですね。

Synflux
シンフラックス 2019年に川崎和也、佐野虎太郎らによって設立された、「惑星のためのファッション」をミッションに掲げる、スペキュラティヴ・デザインラボラトリー。持続可能なファッションを実現するための次世代デザインシステム「Algorithmic Couture(アルゴリズミック クチュール)」の開発と事業化を行なっている。アルゴリズムを活用し、自然環境に配慮した、布の廃棄を最小限に抑え、製造や個々の着用者にフィットした衣服の設計を、さまざまな企業やブランドともに実装している。このほかにもファッションに関わる循環や最適化生産のための研究開発や支援策の提供を手がけている。
次回のEpisode 8では“Unfold A New Chapter”についてお届けします