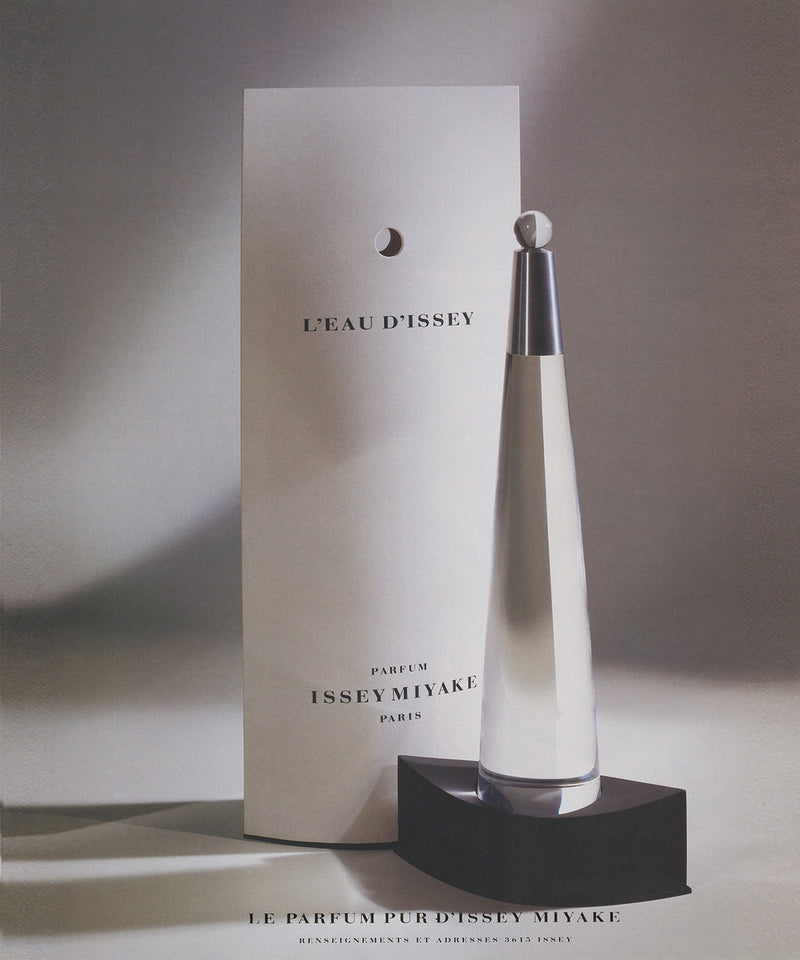Episode 11
2025.10.23
寒川裕人
光と影が紡ぐ、未踏の言語

A-POC ABLE ISSEY MIYAKEは、美術家・寒川裕人 / ユージーン・スタジオの『Light and shadow inside me』シリーズに着想を得た新プロジェクト「TYPE-XIV Eugene Studio project」を発表しました。2025年10月、フランス・パリで開催される「アート・バーゼル・パリ」の期間中、寒川氏とユージーン・スタジオとの特別展示も実現。本プロジェクトは、アートと衣服の交差から新たな表現の地平をひらく試みです。その歩みを、寒川氏との対話を通じて追いました。

寒川氏の作品『Light and shadow inside me』シリーズ。太陽光や光を用いて作られた本作は、光と時間の痕跡を物質として定着させることで、絵画でも写真でもない場所から、新たな表現の可能性を立ち上げている。
──あらためて、今回のプロジェクトが始まった背景をお伺いさせてください。きっかけは、宮前さんが寒川さんの個展『ユージーン・スタジオ 新しい海』(東京都現代美術館/2021-22)をご覧になったことだったそうですが。
宮前義之(以下、宮前) いまでも鮮明に覚えています。私は日頃から時間を見つけてはさまざまな展示を観に行きますが、寒川さんの展示は「もう一度観たい」と思う素晴らしいものでした。不思議な縁だなと思うのは、展示を観たのが、ちょうどISSEY MIYAKEのコレクションのデザイナーを後任にバトンタッチして、新しくA-POC ABLE ISSEY MIYAKE(以下、A-POC ABLE)を始めた頃だったんです。多くの方たちと力を合わせて、三宅が築いてきたものを発展させていきたい──そう思っていた頃に寒川さんと出会いました。そこで寒川さんの、物事の本質を捉えながら、それを言葉に還元できない領域の美としてアウトプットしていく力を目の当たりにして、強い感銘を受けて。そこからA-POC ABLEとして寒川さんとの交流が始まっていくことになりました。

寒川氏のアトリエにて。
寒川裕人(以下、寒川) ありがとうございます。展覧会のあと、色々なお話をしましたね。そのあと、最初にイッセイ ミヤケのオフィスに訪れた際に、TASCHENから出版されている大きな書籍『ISSEY MIYAKE 三宅一生』をいただいて、そこで自分なりに解釈していたと思っていたイッセイ ミヤケという存在のヒストリーを、あらためて探求させていただいたことが記憶に残っています。それで宮前さん率いるA-POC ABLEチームの方々にもアトリエや自宅に来ていただき、共に行ったワークショップが、今回のプロジェクトにつながっていったんですよね。

寒川氏のアトリエで行われたA-POC ABLEチームとのワークショップの様子。
宮前 ワークショップでの題材は、寒川さんの作品である『Light and shadow inside me』シリーズのように自作の青焼き(サイアノタイプ)の紙を折り畳み、それに太陽光が当たることで少しずつ色変化が起きていくものでした。そのときに、私たちはどうしても衣服をつくるときのようにストラクチャーやファンクションを前提に考えてしまいます。けれど、寒川さんは折られた紙そのものの存在や退色によって現れる光と影といった、これまで意識することがなかった視点で美を捉えていました。そこから私たちも立体と平面を行き来し、手を動かしながら、自分たちなりの美を想像して折りの作業に向き合うことができました。それは理屈を超えた楽しさであると同時に、視野を大きく広げてくれる経験だったと思います。

太陽光による退色/色変化を想像しながら、さまざまな折り方を試作している様子。寒川氏のアトリエにて。
──『Light and shadow inside me』をはじめ、寒川さんの作品は具体的な造形を示しながら、その内部には抽象性を抱えているようにも感じます。作品における平面と立体の往復、具体と抽象の往復について、どのように考えていますか。
寒川 実は最初の方、十代半ばの作品は、具体的な描画、絵が多かったですね。それに比べるといまは抽象的に思われるかもしれませんが、技は違えど、そのときから“目”は変わっていないように思います。私にとって作品というものは、個人の体験と進行形の時間を帯びた社会全体、あるいはそこまでに蓄積された長い歴史のひとつの結果であると感じています。具体、抽象という境よりは、そこに「時間」という事実が存在していることが私にとって重要なのかもしれません。例えば今回の『Light and shadow inside me』の青緑色の絵画は、水性インクを塗布した水彩紙を折り、多角形にしたものを固定したまま太陽光に数週間さらし、その後に広げたものです。もうひとつの白黒の作品は、同じ手法で一枚状の銀塩印画紙を暗室で折り、一点の光源で照らして生まれたフォトグラムで、これらのように、描画で表現するのではなく、現象そのものを絵画に体現してもらう、森羅万象を作品の上で起こす、あるいは託している、そのような感覚があります。そういう意味で、紙やキャンバスは身体に近い存在だと感じています。その結果として、平面と立体、具体と抽象のあわいにあるような作品に感じられるのかもしれません。

自宅でのスケッチの様子。
宮前 私は寒川さんの物事の捉え方に強い関心を持っています。あれほど美しい作品や、ダイナミックな発想で構築される空間が、どのような思考のプロセスや視点から生まれてくるのか。イッセイ ミヤケという組織で服をつくりながら、ときどき「なぜ外部とのコラボレーションを続けるのですか?」と問われることがありますが、原動力はやはり人です。寒川さんのような人の隣で、その思考を垣間見て、「こういう視点で物を捉えるのか」「こうして美を見出すのか」と気づかされる。その発見がとても面白いのです。もちろん、すべてを理解できるわけではありません。けれど、その気づきが自分たちのチームに加わることで、私たちはどう変化していくのだろうと。寒川さんと向き合う時間は、そうした問いを抱きながら、とても豊かなものになったと感じています。

ワークショップを重ねることで、互いのプロセスや思考に対する理解を深めていく。寒川氏のアトリエにて。
時間と美しさの新しい捉え方
──お話を伺っていると、寒川さんにとって「時間」という概念は作品に深く結びついているように感じます。それを不可逆なものとして見ているのか、それとも異なる相を見ているのでしょうか。
寒川 ご質問を頂いてふと思ったのは、私は時間を、矢印のように一方向へ進むものとしては見ていないのかもしれないと思いました。たとえば「退色」という現象は、一般的には劣化としてネガティブに受け止めらるものだと思いますが、そうは映らなかった。退色は、色が変化していく進行であると同時に、もとの紙色へ戻っていく後退とも言えます。そこには時間の厚みが存在していて、それがとても美しいと感じたのです。

『Light and shadow inside me』のモノクロームシリーズ。暗室内で銀塩印画紙を折り、1点の光源にさらして制作された白黒のフォトグラムを通して、あらゆる物事が存在するだけで光と影を持ち合わせることが表現されている。
『Light and shadow inside me』の出発点は、2021年の個展で発表した5、6年前でした。ある冬の日、部屋の模様替えをしたときに、偶然手に取ったのは、窓際にずっと置いていた、退色した収納箱でした。一般的には、色の抜けた箱は役目を終え、捨てられるものかもしれませんが、僕には退色した姿がすごく良く見えた。そこに必ず何か可能性を感じ、同時に美があった。染料がはげ、地の色が現れ、理想だった部分とそうではない部分が共存している。その様子に、僕は「人間」のような気配を感じました。
宮前 面白いですね。一般的には、色が落ちることはネガティブに捉えられがちです。染め上がった直後の状態がいちばん美しいとされ、その色を保つために、私たちは職人さんとともに知恵を絞ってきました。

東京近郊の緑豊かな地にあるユージーン・スタジオのアトリエ「Atelier iii」。A-POC ABLEのチームがアトリエの扉を開けると、寒川氏の作品「Everything reflects the shining light toward me (Drawing/Sketch)」シリーズが。
ただ、サステナビリティが求められるいま、物を長く使うために、物と時間の関係をどう組み直すかが、デザイナーに問われている課題のひとつだと思います。20年後や50年後に、必ずしも同じクオリティを保証できない世界のなかで、変化そのものを美に変える力をデザインに取り込むことができれば、いろいろな可能性が開ける。もし着ることで自然に美しい色の落ち方をしていく服が生まれるなら、それはぜひ見てみたい。そのプロセスを通して着る人が服をつくり上げていくという考え方は、イッセイ ミヤケが大切にしてきた美学にもつながりますし、今回のプロジェクトをきっかけに、未来へつなげていきたいテーマのひとつです。「これは美しくない」と切り捨てられてきた事柄も、視点を変えればそこに美を見いだすことができる。世界の見方はまだまだ更新され得るのだと、寒川さんの視点を通して気づかされました。
──そうした気づきが、まさに今回のプロジェクト「TYPE-XIV Eugene Studio project」につながっていきましたが、最終的に衣服となるとき、白と黒。二色の糸のみを用いて、織組織の密度によって染色や色彩に頼らない布のグラデーション表現を実現させました。

白と黒の糸のみで「光と影」を織り出したテキスタイルは、光に応答する銀塩粒子と織物を成す糸とを概念的に重ね合わせる試みとなった。
宮前 最初は「退色」という現象をテキスタイルでなぞろうとも試みましたが、どうしても同じようには再現できなかった。そのなかでイッセイ ミヤケとして何ができるかを見つめ直したとき、織物の最小単位であるタテ糸とヨコ糸に立ち返り、「一本の糸で何ができるか」という問いを置き直したことから、この挑戦は始まりました。白と黒というわずか二色の糸だけを用いて、織りの組織と密度によって光と影の階調を描き出す実践は、印画紙と光の現象を布の言語へと翻訳する挑戦でもありました。
一般的には、その価値を読み解くのが難しい取り組みだったかもしれません。けれども私たちには、これが必ず次につながっていくという予感がありました。タテ糸とヨコ糸を用いた織物の歴史は、1万年近くも続いてきた。人類がこれほど長く布と向き合い続けてきたという事実は、これからも変わらないでしょう。そのなかで物事のプリミティブな部分を理解し、それを生かすことで新しいテキスタイルが生まれ、そこから新しいイッセイ ミヤケの衣服が生まれていく可能性がある。だからこそ今回の取り組みは、小さく見えても大きな一歩になるのではないかと、いま改めて感じています。

実際の作品と仕上がった服を並べて、展示方法について検討している様子。
寒川 A-POC ABLEのチームの方が「このプロジェクトで、新しい“言語”を織っているんです」とお話してされていたことをよく覚えています。布を染めて、糸を染めて望んだ色を作る、それが通常の考え方なのだと思います。けれど、もしそうではない歴史があったとしたら、衣服の在り方は、いまとはまったく違うものになっていた、そのようなお話だったと記憶しています。織り機は、初期のコンピューターや言語の原型といわれるように、両者は連続していて、その意味でも、いま新しい言語を織りなおそうとする試みは、とても興味深いですよね。一方で、はじめて生地を見せて頂いたとき、細かい背景を知らなくとも、明確なクオリティ、手触りを感じたこともよく覚えています。おそらく今回同じような表現を、もっと簡単に行う方法はあったと思うのですが、それでも気の遠くなるような作業を繰り返し、糸の密度だけで色の違いを立ち上げる布を織り上げることをチームの方々は選択された。純粋にリスペクトを感じたと同時に、こういった素晴らしいクリエイションに出会えて嬉しかったです。これはテキスタイルというあり方の中で、非常に深い到達点なのではないかと感じました。
「心地」をつくり出す衣服
──今回のテキスタイルから生まれた衣服は、「アート・バーゼル・パリ」で特別展示されたのち、ISSEY MIYAKE GINZAの展示空間「CUBE」とISSEY MIYAKE SEMBAの「CREATION SPACE」(大阪)でのインスタレーション、さらに各店舗での販売を経て、人々のもとに届けられていきます。この一連の取り組みに込めた思いをお聞かせください。

ユージーン・スタジオのアトリエ「Atelier iii」にて。
寒川 僕が今回強く感じたことは、純粋にチームの方々が作られた衣服がとても美しいということです。直感的に美しいと同時に、衣服を見た、ふれたときに、その奥に何かがあることもまた、説明がなくとも伝わってきました。これは形状も含めて、A-POC ABLEの方々の素晴らしい技の結晶だと思います。展覧会に訪れた人々の記憶には、その体感や衣服の像が残り続けるのではないかと思います。また今回、インスタレーションや全体構成の設計をされた建築家の田根剛さんは、考古学的なアプローチをとられる方ですが、今回、制作過程のアーカイブや作品の道具を考古学的に──あるいは現代を掘り下げるという意味では「考現学的視点」と言うべきかもしれませんが、キュレーションし、扱ってくださったことで、このシリーズや、普段は見せることのない道具やプロセスを、さまざまな角度から見ることができる非常に興味深い機会にもなりました。

インスタレーションデザインは、パリを拠点とする建築家・田根剛氏(ATTA)が担当。写真は、田根氏、A-POCチームとともに展示構成を検討中のユージーン・スタジオのアトリエ「Atelier iii」での一場面。
今回は展示という形を通して、一人ひとりに丁寧にメッセージ、プロセス、衣服を届けていくことに自然と辿り着いたように思います。そこには宮前さんがおっしゃっていた「長く愛される衣服を」という考え方と通じると思っています。
宮前 イッセイ ミヤケが一貫して大切にしていることは、つくるものの先に人の営みがある、すなわち「人が中心にある」という価値観です。そのために欠かせないのが「心地」です。建物なら居心地、服なら着心地、道具なら使い心地。最後に大切にすべきなのは、そうした感覚なのだと思います。

寒川氏の作品制作に使用した道具。
三宅がよく口にしていたのは、「長く愛されるものをつくらなければならない」という言葉でした。ファッションには、いまこの瞬間を輝かせる一方で、消費され、すぐに失われてしまうという側面があります。それが時代をつくり出す力にもなるのですが、その対極にあるのは生活のなかで長く使われ続ける衣服であり、そのためには「心地」が不可欠です。その心地は、単に機能性を満たすことを超えていく。新しい自分に生まれ変われる、自信を持てる──今回で言えば、寒川さんとの物語が宿ったA-POC ABLEの衣服に触れ、そのストーリーを思い描きながらまとうことで、まったく違う感情が立ち上がってくる。そうした体験を生み出すことこそ、デザインの大切な仕事だと思います。そして、その心地をきちんと生み出せるかどうかが、良い服か否かを分けることになると思います。だからこそ、今回のプロダクトが人々の手に渡り、心地の生まれる瞬間に立ち会えることを願っています。着る人にとって特別な衣服となり、長く愛される存在になってほしいと強く思います。

本プロジェクトでは、コート、ブルゾン、ストールの3アイテムを展開。
寒川 宮前さんたちとご一緒して感じたのは、イッセイ ミヤケの精緻で職人的でありながら革新性に満ちた仕事が、「人間が中心にある」という強い信念によって支えられているということでした。私の作品も人の可能性を信じ続けるところから生まれてきます。その一致をみたことが、印象深かったと感じています。表現の核にあるのは人間の存在であり、それが衣服というかたちで具体化されている──今回のプロジェクトからは、その哲学を改めて実感しました。
寒川裕人 / ユージーン・スタジオ
1989年、アメリカ生まれ。時間や存在、歴史といったテーマを題材に、抽象的な絵画やインスタレーションを制作する。東京都現代美術館で開催された個展「ユージーン・スタジオ 新しい海」(2021–22)は、同館史上最年少での開催として注目を集めた。その後、同展を原型とした約1ヘクタールの常設美術館が、アジア・ASEANにゆかりのある複数のコレクターにより、バリ島の世界遺産の麓に建設されるなど、国際的な展開を見せている。主な展覧会に、金沢21世紀美術館「de-sport:」(2020)、サーペンタイン・ギャラリー(ロンドン)「89+」(2014)など。映像作品も手がけ、アメリカで発表した短編映画はロードアイランド国際映画祭やブルックリン映画祭をはじめとする複数の映画祭で公式選出・受賞を果たした。現在は、本人とスタッフの手で設計・施工された約700㎡超の空間「Atelier iii」(東京近郊)を拠点に、さまざまな分野のスタッフとともに制作を行っている。