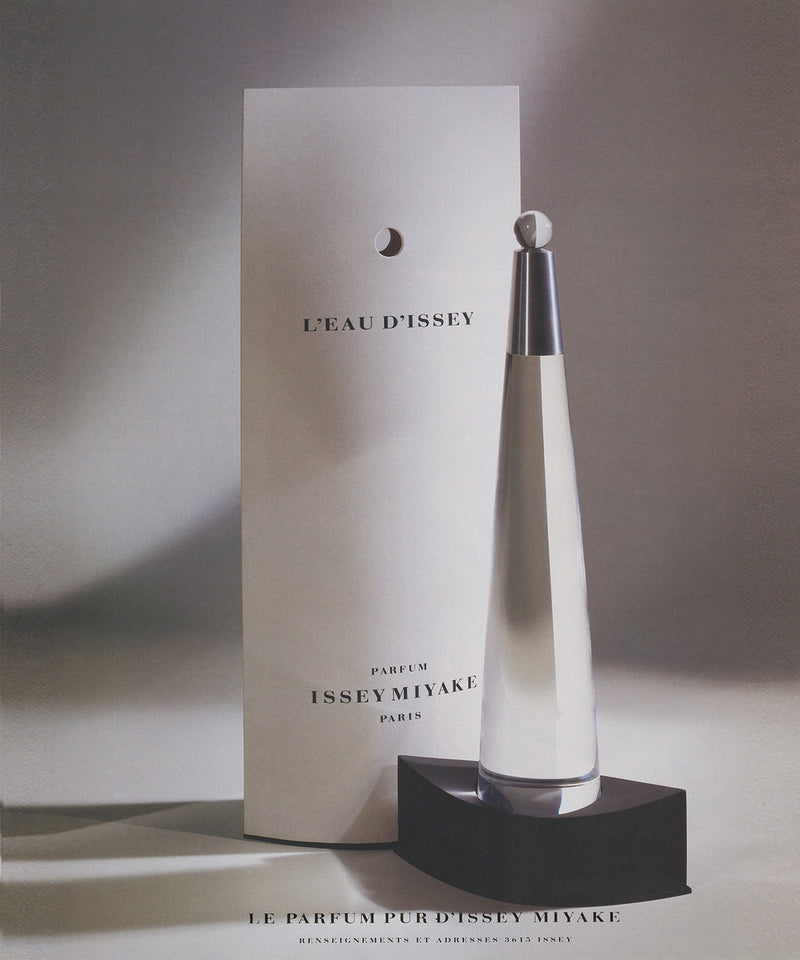Episode 6
“On a Single Plate”
by Yuri Nomura (eatrip)
美味しい食事と心地よい衣服には、どうやら共通点があるようです。例えばいずれも、素晴らしい素材と得難い人との出会い、豊かなコミュニケーションが息づくこと。さらにeatripを主宰する野村友里の場合は、誰もが楽しめるようなオープンな空気に満たされた場をつくり、一見すると交わることがないような才能を結びつけていきます。A-POC ABLE ISSEY MIYAKEのデザイナー、宮前義之は「まるでひとつのお皿に載った見たことのない料理のよう」だとも。長く親交を温めてきたふたりの対話をお届けします。

東京・表参道の「GYRE」。ハイファッションのブティックが軒を連ねるビルの4階に、ひときわ異質というか気取らぬ空間が拡がっています。「eatrip soil」。生産者、野生、食材の旬を大切にして、食が本来もっているはずの、力強さ、つまり美味しさを伝えてきたeatripの野村友里が、2019年11月にオープンしたグロッサリーストアです。
日本全国から届けられる調味料や発酵食品、作家が手がけた器やカトラリー、土がついた季節の野菜。食べることは生きることであり、何かを買うことは投票することであり、つまり未来を選ぶこと。ここにはあるいは規模は小さいかもしれないけれど、ピンと筋の通った生産者たちが手がけたものだけが並び、併設された小さな庭には、柔らかな土壌からハーブや果物の木が育っています。
なにしろ「人生は食べる旅」。eatripの思いがとことん反映されたお店の隅の小さなテーブルで、対話は交わされていきます。柔らかな日差しと、静かに流れるレコードの音。ふたりは会うなり楽しそうでした。

野村 友里(以下、野村) 私もA-POC ABLEの服を着させてもらっていて、すごく合理的だなって思います。洗濯機で洗えるし、シワにならないし、軽いし。パッと見た印象は、ものすごくとがってる服で、自分には似合わないかもというイメージが強かったんです。でも宮前さんに会って着るようになって。こんなに自分や身体を解放する服ってあるんだ、と驚きました。なんて言うか、すごくいろんなことを教えてもらえます。身体の感覚的なことや、いい意味での合理性と生産性のことや、ものをつくるプロセスとか。
宮前 義之(以下、宮前) ありがとうございます。友里さんとは僕がISSEY MIYAKEのデザイナーをしていた頃に知り合ったんです。年2回やってくるコレクションのスケジュールの中で、ひたすら服をつくっていて。その時期には当然、悩みもいろいろありました。そんな時に、友里さんと会ってお話したりすると、「あ、このことを言ってたのかも」と後からじわじわ感じることが多々あって。
友里さんが向き合っているのは食べることや料理で、友里さんがしばしば話していますけど、食というのは身体と心を形成するのに欠かせないものです。一方で僕は服やものづくり。違いももちろんありますが、かつて三宅も似たようなことを話していたのを憶えています。身体にとって心地よくて、気持ちまで変えていく衣服というものについてです。僕自身はそれがどういうことか、感覚的にわかるようになるまで時間がかかったし、友里さんからたくさんヒントをもらったとも思っています。
野村 ありがとう。光栄というか恐縮ですけど。
宮前 食というのは、料理や食べることを通じて人と人をつなげたり、食材を通じて土壌や自然と人をつなげたりするものですね。すごいなと思うのは、友里さんはそういうことを、分野や地域を自由に越境してどんどん拡げているように見えるから。僕も3年前にA-POC ABLEをスタートして、服やものづくりを通じて、いろんなことをつなげていき、可能性を拡げていくことにチャレンジしています。
衣食住の食や衣という人の生活に身近なところで、そういう活動をしていくことが、これからの時代にとって大事なことだし、デザインの仕事なのではないかと思っています。そう考えると、友里さんが自然とやってきたことって、僕らにとっても学びがあると思うんです。
最終的には素敵な音楽をきいて、美味しい食事をして、好きな服を着て楽しめたらいい。でももちろん、その手前の準備にはすごいエネルギーをかけているし。それがものをつくる本質というか、大事なことなんだろうなって思うし。どんなものでも簡単につくろうと思えばできるような時代に、その手前にあるエネルギーを伝えていけたらと思っていて、友里さんに会いにきました。

──これまでの「DIALOGUES」でも、宮前さんは食べ物で例え話をすることが多いですよね。
宮前 そうかもしれません。社内でも商品構成を検討するときにはカロリーで話したりします(笑)。「これはハイカロリーだね」とか。あと毎日着るような服を、パンやお味噌汁のように考えたり。着てくれる人の意識や気持ちが、生活の中で具体的にどう動いていくかということを、ちゃんと想像できていないと、服づくりは自己満足になってしまいかねない。なので生活の中でどのような位置にあるべき衣服かを考えるうえで、そういった例え話もしますね。食べ物は感覚が共有しやすいので。
野村 なるほど。白米のような商品もあるんですか?
宮前 そうですね、例えばイッセイ ミヤケのなかではPLEATS PLEASE ISSEY MIYAKEの商品はそうかもしれません。
野村 さすが。すぐに答えが出てきた(笑)
宮前 究極のおにぎりだなって思うことがあります。BAO BAO ISSEY MIYAKEもそうかもしれません。なんて言うか、毎日食べても飽きないと思うんです。どこでも、誰でも、着たり使ったりできるような。きっとおにぎりみたいに、世界中の人が美味しいと思ってくれる。あるいはフランスのバゲットみたいなものとも言えると思います。
もちろんそれぞれのブランドの中にも「おにぎり的な商品」を用意していると思います。ハンバーグステーキとか、それぞれの得意なレパートリーやメインディッシュもつくっていく。ハレの日に着たくなるような特別な服も必要ですが、やっぱり絶対に、美味しいご飯を炊かないといけない。そこをみんなでつくっていきたいと思っています。といっても美味しいごはんを炊くことは、シンプルだからこそ一番難しいのですが。
野村 そうか。PLEATS PLEASEがおにぎりなんですね。確かに、ごはんを最高に美味しく炊くのは難しいです。お米の種類、水、何でどうやって炊くのか。しかもそれを毎日だから。考えれば考えるほど、PLEATS PLEASEがごはんに思えてきました(笑)
宮前 ごはんですよ。90年代からずっとつくられ続けてきて、いまでも世界中のさまざまな世代の人が着てくれている。世界のごはんになったので。
野村 そういえば、宮前さんがISSEY MIYAKEのコレクションをやっていたとき、プリーツとどう向き合うべきか悩んでいたことがありましたよね。
宮前 そうでした。ブランドのファンのみなさんはプリーツの服を望んでいる。けれどファッションの世界はつねに新しいものを求めています。自分自身も新しいことに挑戦していきたいという思いもありますし。だからとても迷っていた時期がありました。
野村 それであるとき、白米は白米。永遠にごはんだからっていうような気持ちというか。僕たちの主食なんだと腹落ちして、そうしたら途端に楽になったという話を聞いたんです。
宮前 はい。つまり素直に向き合えるようになったんです。そして新しい気持ちでコレクションと向き合えるようになっていきました。
野村 宮前さんのその話がとても好きです。というのも、新しいとは何かという問いは、私にもつねにあるから。私は自分も変わっていくことが大切なんだと思うようになったんです。自分が見方を変えたら、どんなものだっていつも新しく見えてくるから。対象物を新しくするだけではなく、自分も変わっていけばいい。そうしたらつねに新しくいることができるはずだなと思ったんです。同じ食材や調理の仕方だとしても、何度も新しい出会いができるなって。
お米とかごはんは特にそうなんです。毎回、うわー美味しそう!とか。美味しく炊けたなとか。見方によっては心が動く。ほかの食材だって旬になると、わぁそら豆はやっぱり最高とか、きゅうりって美味しいなとか、そういう気持ちになれるじゃないですか。お米だってそれと一緒なんだと思う。生きている食材は、毎回が初めまして。どんな時期にも初物や旬があるし、一期一会だから。
──eatripの活動やイベント、このeatrip soilのお店もそうですが、野村さんのやってらっしゃることを見ていると、A-POC ABLEのチームづくりや、仕事のやり方が、似ているようにも感じます。それはやはり野村さんからヒントを得ているからでしょうか。
宮前 友里さんと話すと、なんか不思議と後からじわじわじわじわ効いてくる感じがします。遅効性というか、本質的すぎるのか、「それはそうだよな」と当然のことのように聞いてしまう。けれどしばらくして、それが自分のこととして重なってくることが多くて。「あぁこのことだったのか」と思い出すことがあります。
野村 そうなんですね。それはきっと宮前さんがうまく拾って憶えてくれてるからだと思います。
宮前 それに友里さんを見ていると、すごく場を大事にしているように感じます。以前ちょっとご一緒させてもらったイベントでも、とてもオープンな空間が拡がっていて。料理する人や、音楽をする人、踊る人とか、僕らみたいなものづくりの人とか、普通の場ではつながらないようなものごとが混ざっていくような感覚があります。まるでひとつのお皿に載った見たことのない料理のような。それがもはや定義できないものになっているのが、面白いところなのかもしれません。
それに、僕たちは最近、自分たちのものづくりのことを「journey」と形容することがあります。旅として捉えることも、友里さんがやってきたことですね。食材を探したり、人と出会ったりするストーリーとともに食が豊かになるように、A-POC ABLEもいろいろな人や素材と出会いながら、新しいインスピレーションを得て、物語を紡いでいきたいと思っています。
──多彩な人が自由に集まることのできる場をつくることや、異分野の人とつながることは、多くの人が実現したいことだと思います。それを実現させていくには、何が大切だと思いますか?
野村 難しいですね。もしかしたら、境界線をつくってしまうのが、そもそも変な話なのかもしれません。みんな人間だし、人間がやっていることだから。いつのころからか、料理家、音楽家、デザイナーとか、分担や分業が当然になっていますけど。だから私はまず人として話すことから初めているのかもしれません。なんの境界もないところから。もちろん、それぞれの人には仕事や表現したいことはあるけれど、それはその人の先の先の最先端のところにあるというか。それ以外のおおもとになっているところは、人として共通しているところがいっぱいあるんだと思います。つまり職業や仕事としてではなく、人として会えるかなんだと思う。
宮前 確かにそうですね。会社でもヒエラルキーのなかにいては心を開いて話せません。僕も異分野の方々とお話しするときは、境界を意識することなく話したい。だから友里さんのおっしゃったことはとても大事にしていますね。本当に。自然に出会い、興味があることについて話して、いつの間にかこんなことできたら面白そうですねとなっていく。A-POC ABLEのプロジェクトでは、そういったケースが多いですね。
野村 いいなぁ。何だか楽しそうな話ですね。
宮前 そうです。楽しいですよ。ひとつのプロジェクトでだいたい2〜3年は要してしまいますが。ゆっくり人として話しているから、本質的なところでお互いの興味や関心が結びついていくような気がします。そうではないと、テーマを決めて、スケジュールと予算を決めてとなっていってしまう。ときにはそういう方法が必要なこともありますが、そればかりでは、お互いに仕事としてしか話すことができなくなってしまいます。僕はできるだけニュートラルな状態でいたいと思っているんです。何か面白いと思ったことや人と出会ったときに、さっと動くことができるように。

──野村さんと宮前さんの対話を聞いていると、普段の生活や人として生きることなど、誰もが共通してもっていることの大切さを改めて感じます。生活や人との誠実な向き合い方というか。
野村 なるほど。でもそんなに大袈裟なことでもないかもしれませんよ。私はそもそもいい加減なんですよね。なんていうか「楽しみたい派」なので。
宮前 楽しいことと、食や生活や人への向き合い方が重なっているのかもしれませんね。このお店がオープンした頃は大変だったと思うけど。
野村 そうですね。開店したのはパンデミックの前だったんですが、それでも賛成する人はひとりもいなかったんです。開店資金を工面するのも難しかったし。それでもなんとかオープンしたら、3カ月後にウイルスがやってきました。ここのビル自体は営業を停止していましたが、このお店だけは生活に必要なものを扱っていたから、開けておくことができました。そうしたらみんなが来てくれて、ここで1日過ごしたり、庭の手入れをしてくれたり。あと男の子がやってきて、自炊しなきゃいけないから出汁をとりたいんですと言ってくれたり。
だからすごく人との距離が近くなりましたし、その時間はいまから思えばとても得難いものでした。もし自分がせねばならないこと、自分に課せられたことがなくなったときに、やっぱり人はもっと手触りがあるような、時間がかかることをしたくなるんですね。レコードがすごく売れるようになったみたいに、土いじりをしたくなるんです。そういう経験をできたから、このお店はもう大丈夫だと思っています。
宮前 顔の見える人の生活の一部になっているっていう実感が、このお店で育まれたんですね。生活の一部になるっていうのは、簡単なようですごく難しいことですから。
野村 けれど結局、パンデミックが落ち着いていくと、暮らし方も以前と同じように戻っていったような気がする。むしろ加速したかもしれません。でもこんなスピード感は決して続かないと思うんです。とはいえ私たちも臨機応変だから、そのなかで面白いことや楽しいことを見つけてきたりもしますけど。東京にはたくさん人が住んでいて、みんながそれぞれ理由があって、いろんな暮らし方をしています。多分このお店がこうやってあり得ているのも、パンデミックの後のみんなの生活の中のグレーゾーンのようなところで、「ちょっと生活にいいことをしてみよう」という気持ちを通じて入ることができているからだと思うんです。
──どんなときでも、楽しさと生活に対する真面目さをキープし続けているかのような。
野村 そうかもしれません。楽しい真面目な人。楽しい景色と時間は、本当にいっぱい経験することができてきたと思うから、それはありがたいと思っていて。きっとみんなが一緒につくってくれた、そういう時間のおかげなんですよ。
宮前 そういうところに僕はもしかしたら憧れるのかもしれません。世の中にはいろんな料理人がいらっしゃると思います。朝から晩までキッチンの中でずっと自分のレシピを追求している人もいるだろうし、キッチンから飛び出していろんなものに出会いながらひと皿を作る人もいる。どっちも素晴らしいと思いますが、友里さんを見ていると、自分もやっぱり外にどんどん動いていきたくなるんです。さっきのお話じゃないけど、人と出会い、景色が変わり、自分自身の視座が変わっていくような楽しさを、ものづくりに反映させていきたいんです。
野村 私もそうやって人と共鳴し合ったときが、たぶん最高に幸福というか、豊かな気持ちになります。共鳴って測れないし、正確にはわかりません。感覚からくるものだから。でもね、空気全体が揺れたりするんですよ。本当に。一方通行じゃなくて。誰でもきっとそういう時間が愛おしくて、服をつくったり、料理したり、記事を書いたりして、その向こう側にいる人につながりたいと思ったり、願ったりする。そういったことを大なり小なり積み重ねていくことが、生きることってそうなのかなって思います。
食事というのは、そういう嬉しさや共感をちょこちょこ発生させやすいんですよね。家庭の中でも、レストランでもきっとそう。実際にそういう瞬間が自分のなかにもたくさん生まれてきたから、それをどう恩返ししていくかを考えています。でもね、その恩返しもまた楽しいんですよね。

YURI NOMURA
野村友里 料理人/eatrip主宰。長年おもてなし教室を開いていた母の影響で料理の道へ。ケータリングフードの演出や料理教室、雑誌での連載やラジオ出演に留まらず、イベント企画など食の可能性を多岐にわたって表現している。生産者、野生、旬を尊重し、料理を通じて食の持つ力、豊かさを伝える活動をしている。eatrip soil(表参道)eatrip kitchen(祐天寺)を運営、著書は『とびきりおいしいおうちごはん』(小学館)
次回のEpisode 7では“Taking Detours with AI”についてお届けします